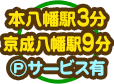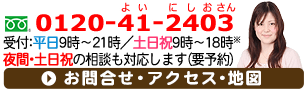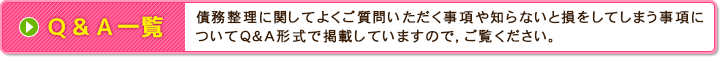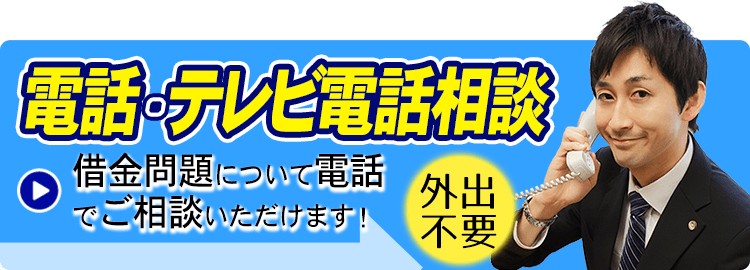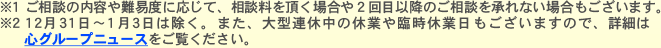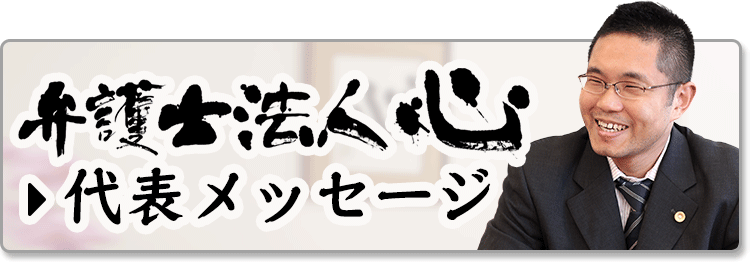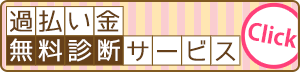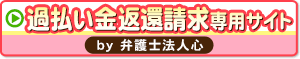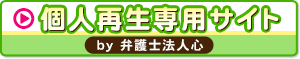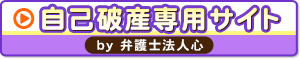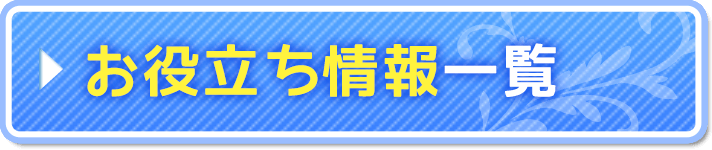「債務整理」に関するお役立ち情報
保証債務とは?保証人の義務が発生するリスク・対処法
「保証債務」という言葉を聞いたことはありますか?
保証債務は、誰かの借金(借入)保証人になっている人にとっては重要なもので、保証人になる前にその内容を詳しく知っておく必要があります。
ここでは、保証債務や保証人について、抱えるリスクや請求を受けた場合の正しい対応(借金を抱えてしまったときの解決法)について解説します。
1 保証債務とは?
保証債務とは、「主たる債務者が債務(借金を支払う義務)を履行できない時に、保証人が主たる債務者に代わって債務を履行する義務」のことです。
分かりやすくいえば、借金をした本人が返済できなくなったとき、保証人がその支払をするという義務を意味します。
自分が借金をしていなくても、家族や親族、友人の保証人になっているという人は少なくないと思います。
奨学金の保証人、事業のための借入の保証人、家や車のローンの保証人など、その種類は様々でしょう。
保証債務の特徴は、ある日突然、忘れた頃に莫大な請求がくるケースがあることです(主たる債務者が前もって保証人へ滞納を知らせることはまれです)。
保証人は自分のものではない多額の借金を支払わなければならないわけですから、資金が十分にない限りは当然ながら生活に大きな影響が生じます。
そのため、「保証人になってほしい」と頼まれても、親切心だけで応じるのは絶対に避けるべきといわれているのです。
二つ返事で了承をせず「もし本人が返済できなくなったときに、どのような事態になるのか」を理解して、万が一のときには自分が責任を取れると確信できる場合のみ応じましょう。
ちなみに、借金は家などの財産を担保にすることがあり、これは物的担保と呼ばれます。
これに対し、保証人の財力を担保にする場合は人的担保と呼ばれます。
2 保証債務の成立要件
保証債務が成立するには、以下の要件が必要です。
⑴ 主たる債務があること
保証債務が成立するには、保証を受ける債務(=主たる債務)があることが条件です。
例えば、主たる債務が完済される・時効が成立するなどして消滅した場合、保証債務も同時に消滅します。
⑵ 契約が成立していること
債権者と保証人との間で保証契約が成立していることも条件です。
通常、保証人は主たる債務者から依頼されるので、保証人は債務者と契約をしていると思いがちです。
しかし、主たる債務者と保証人との間で交わされるのは「保証委託契約」です。
実際に保証人が「保証債務の契約」を交わす相手は債権者であり、主たる債務者ではありません。
保証債務が成立するには、この契約関係が成立していることが前提となります。
⑶ 書面の記録が存在すること
保証債務は書面での記録が必要です(コンピューター上の電磁記録でもよい。)。
書面にするのは、あとで言った・言わないとならないようにするためです。
仮に保証契約が口頭でなされたとしたら、そうしたトラブルは不可避でしょう。
また、保証人として借金を肩代わりするのは非常に大変なことです。
その結果の重大性を考えると、保証人は熟慮の末に名を連ねるべきということから、2004年の民法改正により書面記録が必須となりました。
⑷ 保証人に保証能力(経済力)があること
保証人となるには保証能力があることも条件です。
保証能力とは財力・経済力のことで、万が一の時にしっかりと返済できる人でなければ保証人となる意味がありません。
債権者としては、無職の人や住所不定の人を保証人にすることを認めないでしょう。
また、未成年者は親の同意がないと保証人にはなれないので、一般的に再建者が未成年者を保証人と認めることはありません。
3 保証人の保護のために認められた権利
主たる債務者が支払不能に陥ったとき、保証人は保証債務に従って借金を支払わなければなりません。
しかし、保証人になっただけで借金の尻ぬぐいを無条件でしなければならないのは、余りにも酷な話です。
そのため、保証人には、一方的に弱い立場に置かれないよう、以下の権利が認められており、債権者からの請求に対抗することができます。
⑴ 催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対して支払を請求してきたときに「先に主たる債務者に請求をしてください」と主張できる権利のことです。
しかし、催告の抗弁権は、主たる債務者に催告(借金返済を請求)するだけでクリアできるので、債権者にとってはほとんど問題になりません。
ただ、催告の抗弁権により保証人は一時的に責任を回避することが可能です。
なお、主たる債務者が行方不明になって連絡がつかない場合や、主たる債務者に破産手続が開始している場合は、保証人は催告の抗弁権を主張することはできません。
⑵ 検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債権者が保証人に対して支払を請求したときに「債務者はまだ財産があるので、請求は債務者にしてください」と主張できる権利です。
しかし、検索の抗弁権を行使するときには、保証人が債務者の財産を立証しなければなりません。
例えば、ある債務者Aが債権者Bに対して90万円の借金をしており、その支払ができなくなったとします。保証人は、債務者Aの知り合いのCとします。
このとき、保証人Cが検索の抗弁権を主張し、債務者Aに50万円の預金があることを立証した場合は、債権者BはAに50万円を請求すべきということになります。Aが支払に応じない場合は、Aの銀行口座を差し押えて債権の回収をします。
このとき、保証人Cが負うべき保証債務は差額の40万円だけです。
また、債権者Bが取り立てを迅速に行わなかったことにより、別の債権者Dが銀行口座を差し押さえて50万円を回収した場合、その責任は債権者Bが負わなければなりません。
この場合も、保証人Cが負うべき保証債務は40万円だけで、それ以上請求されることはありません。
⑶ 分別の利益
保証人が複数人いる場合は、保証債務は保証人の頭数で割った額になります。
例えば、90万円の債務に対し保証人が3人いる場合、仮に保証人に請求がいったとしても、各30万円ずつ負担すればよいことになります。
⑷ 求償権
求償権は、保証人が肩代わりした借金を主たる債務者に請求できる権利です。
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益は、債権者が保証人に請求をした時点で発生するのに対し、求償権は保証人が支払をした後に発生します。
しかし、求償権があるからといって、肩代わりしたお金が戻ってくるとは限りません。
そもそも債務者は支払能力がないから保証人に迷惑をかけているわけで、保証人が求償権をもとに請求しても、支払ってもらえる可能性は低いと考えられます。
4 通常保証以外の特殊な保証
ここまで解説した保証債務はいわゆる「通常保証」の内容です。
しかし、保証契約は通常保証以外にもいくつかあり、特殊な契約については特に注意が必要です。知らないうちに保証債務を引き受けると大きな不利益を被る可能性がありますので、十分理解しておきましょう。
⑴ 継続的保証
継続的保証は、「一定期間だけ保証する」というもので、信用保証・身元保証などが該当します。
身元保証などは就職等のときに必要で、通常は親兄弟など親族がなりますが、同居親族以外の第三者と指定されることもあります。
保証期間は基本的に3年、長くても5年程度です。
身元保証に関しては債務保証でないことに加え、就職のお祝いムードもあり、気軽に引き受けるケースも多いのです。
しかし、万が一本人が雇用先で損害を与えた場合は、保証人が責任を負わされる可能性もあります。
⑵ 共同保証
共同保証は保証人が2人以上いるケースです。
仮に主たる債務者の借金が300万円だった場合、共同保証人が2人なら、それぞれ150万円ずつ保証することになります。
⑶ 連帯保証
保証人になるときに最も気を付けなければならないのは「連帯保証」です。
連帯保証人は保証人に比べて重い責任を負うことになるのですが、現在の日本ではそのほとんどが連帯保証契約とされるのが一般的です。
保証人には上述したように、債務者が支払をしないときにも抗弁権などで債権者に対抗することができます。
しかし、連帯保証人にはこうした権利は認められていません。
連帯保証人は基本的に債務者と同じ立場に立ち、主たる債務者が払えないときは主たる債務者と同じ責任を負い、支払を求められた場合は抗弁せずに支払いをしなければなりません。
なお、これは連帯保証に限ったことではなく、通常保証でも同様ですが、主たる債務者が個人再生や自己破産で返済義務がなくなったとしても、保証人は免責された分の借金の支払義務を継続して負うことになります。
もし、保証債務の支払ができない場合は、債権者に強制執行される前に保証人も債務整理することを検討する必要があるかもしれません。
5 連帯保証人と保証人の違い
⑴ 連帯保証人は抗弁権がない
連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。
そのため、債権者からいきなり請求をされても一切の反論ができず、無条件で保証債務の支払に応じなければなりません。
ただ、債権者もまずは元債務者に支払請求をして、これに応じてもらえない際に初めて連帯保証人に連絡をしてくることがほとんどですので、その点はご安心ください。
⑵ 連帯保証人は分別の利益がない
連帯保証人には分別の利益もありません。
仮に100万円の負債がある場合、保証人が2人いるならば分別の利益により50万円ずつ負担すればOKです。
しかし、連帯保証人の場合は、保証人が複数いても一括で100万円支払う義務を拒否できません。
6 まとめ
このように、保証人・連帯保証人は本債務者が支払不能となった時に大きな不利益を受けます。もし保証人として印鑑を押してほしいと頼まれても、契約内容をよく確認し、サインをするかどうか慎重に判断しましょう。
もし、すでに保証債務の請求がきていて、かつどうしても支払えない場合はすぐに対処する必要があります。
放置していると、主たる債務者と同様に法的措置を受けて財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
当法人は、保証人の方の債務整理の実績も豊富です。
現在、保証債務のことで困っている方は、どうぞご相談ください。
それぞれの方の状況に合わせて、ベストの解決方法を提示させていただきます。
債務整理に関する相談は原則無料ですので、お気軽にご連絡ください。
ETCパーソナルカード-ブラックリスト入り後も使えるETCカードとは 債務整理を自分で行うことのリスク・デメリット